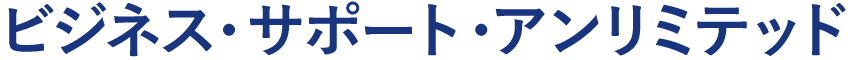前回(2024/11/18付け)も「スモールM&A」について言及し、その際「スモールM&Aの担い手として、個人の進出が顕著で、実は、新しい日本のビジネススタイルが、今、産まれつつあるのかも知れません…」と書きました。
今回はスモールM&Aの実態をもう少し掘り下げ、別の角度から見ていきましょう。
スモールM&Aの公式定義はありませんので、このブログでは、引き続き、主として「譲渡価格が1億円程度以下のM&A」として、この用語を使用します。
つまり、ここで言及するスモールM&Aの当事者は中小企業とは限らない点が一つのポイントです。
スモールM&Aの本質とは

スモールM&Aを譲渡金額が1億円程度以下の相対的に少額なM&Aと定義することによって、見えてくるものがあります。
まず、中企庁の定義する「中小M&A」と異なり、当事者には大企業も含まれます。
正確な統計はありませんが、大企業が中小企業を買収することも、逆に自己の一部門を売却することも、まま見られる現象です。大企業が自己の一部門を売却する際は多くの場合、「カーブアウト」として、企業分割・企業譲渡ではなく事業譲渡の貌を取ります。
当然、大企業同士の事業譲渡であってもスモール規模のものもあります。
一方、法人化していない個人事業主自身の企業売却は当然に事業譲渡になります。
勿論、中小企業同士のM&Aでも様々な理由で企業譲渡(株式譲渡)でなく事業譲渡の形式は使われます。
かくて、企業譲渡(株式譲渡)に加え、事業譲渡によるものが増加していきます。
先日のブログでも申し上げたとおり、件数においては、スモールM&Aが全体M&A件数を牽引している側面がおこっています。
当事者が中小企業にまで広がったことと、M&Aが身近な存在になったことに起因するものと思われます。
M&Aにおける株式譲渡と事業譲渡の法的・実務的相違点についてはここでは割愛します。このスモールM&A議論においては事業譲渡が多い分だけ、結果的に、相対的に金額がスモール化したことを述べるにとどめましょう。
単に金額が小さくなっただけで、それで日本の産業が変わることなど、ある訳ないじゃないかとお思いの方も多いと思います。勿論、変化は急激に起こる訳ではありません。
そもそもM&Aは所詮、目的ではあり得ず、手段に過ぎません。
ただ、企業(事業)を適正価格で手に入れる為には、財務・税務・法務・労務・人事・金融他様々な要素を検証する必要があり、その為に専門家を頼れば、自ずとその報酬(含む「ミニマムチャージ」)は高止まりし、結果的に、それは実施されるM&Aの価格自体にも反映されてきました。しかし、今、M&A価格そのものも報酬価格も同時並行的にスモール化が進んでおり、それが更に一層のM&Aの普及を呼び、現在のスモールM&A、そしてM&A全体が増加しているのと見ています。
そこでは企業が起死回生の為、自らのビジネスの転換を賭けた大博打に失敗した前回の東芝の失敗例は過去のものになりつつあり、
「企業自体を買う」と言うより、当該企業の有している「特定の資産・ノウハウ・市場・技術を手に入れる」と言う本来のミッションの為、なるだけコンパクトな形で事業継承または企業買収を行うことは当然であり、それが更にM&A金額の少額化の一因となっているのでしょう。
そして、M&Aがスモール化することで、何が一番変わるのかと言えば、それは(M&Aについて売り手、買い手とも)「使い勝手が抜群に良くなること」であると思われます。
次章では、その典型例をみてみましょう。
まず、中企庁の定義する「中小M&A」と異なり、当事者には大企業も含まれます。
正確な統計はありませんが、大企業が中小企業を買収することも、逆に自己の一部門を売却することも、まま見られる現象です。大企業が自己の一部門を売却する際は多くの場合、「カーブアウト」として、企業分割・企業譲渡ではなく事業譲渡の貌を取ります。
当然、大企業同士の事業譲渡であってもスモール規模のものもあります。
一方、法人化していない個人事業主自身の企業売却は当然に事業譲渡になります。
勿論、中小企業同士のM&Aでも様々な理由で企業譲渡(株式譲渡)でなく事業譲渡の形式は使われます。
かくて、企業譲渡(株式譲渡)に加え、事業譲渡によるものが増加していきます。
先日のブログでも申し上げたとおり、件数においては、スモールM&Aが全体M&A件数を牽引している側面がおこっています。
当事者が中小企業にまで広がったことと、M&Aが身近な存在になったことに起因するものと思われます。
M&Aにおける株式譲渡と事業譲渡の法的・実務的相違点についてはここでは割愛します。このスモールM&A議論においては事業譲渡が多い分だけ、結果的に、相対的に金額がスモール化したことを述べるにとどめましょう。
単に金額が小さくなっただけで、それで日本の産業が変わることなど、ある訳ないじゃないかとお思いの方も多いと思います。勿論、変化は急激に起こる訳ではありません。
そもそもM&Aは所詮、目的ではあり得ず、手段に過ぎません。
ただ、企業(事業)を適正価格で手に入れる為には、財務・税務・法務・労務・人事・金融他様々な要素を検証する必要があり、その為に専門家を頼れば、自ずとその報酬(含む「ミニマムチャージ」)は高止まりし、結果的に、それは実施されるM&Aの価格自体にも反映されてきました。しかし、今、M&A価格そのものも報酬価格も同時並行的にスモール化が進んでおり、それが更に一層のM&Aの普及を呼び、現在のスモールM&A、そしてM&A全体が増加しているのと見ています。
そこでは企業が起死回生の為、自らのビジネスの転換を賭けた大博打に失敗した前回の東芝の失敗例は過去のものになりつつあり、
「企業自体を買う」と言うより、当該企業の有している「特定の資産・ノウハウ・市場・技術を手に入れる」と言う本来のミッションの為、なるだけコンパクトな形で事業継承または企業買収を行うことは当然であり、それが更にM&A金額の少額化の一因となっているのでしょう。
そして、M&Aがスモール化することで、何が一番変わるのかと言えば、それは(M&Aについて売り手、買い手とも)「使い勝手が抜群に良くなること」であると思われます。
次章では、その典型例をみてみましょう。
某芸能事務所が仕掛けたM&Aの「狙い」と「お釣り」
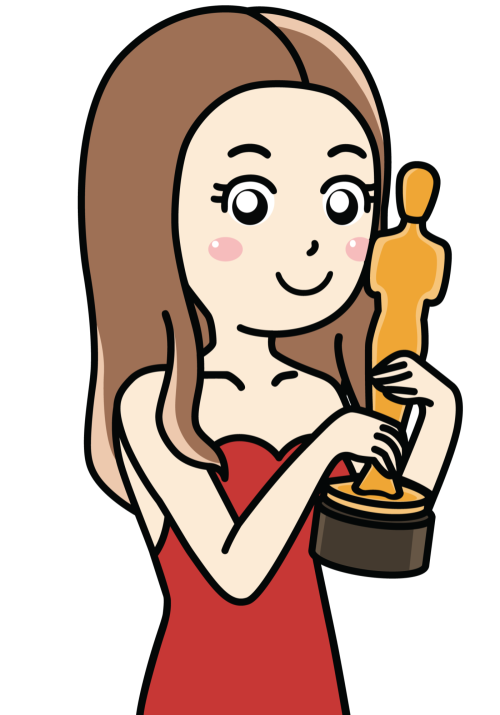
このM&Aは結構、業界内では有名な話ですので、実名で記載しても差し付かえないとは思いますが、ここでは敢えて、匿名のフィクション仕立てでご披露しましょう。
その日、個性派俳優として知られるKは、公共放送の朝の帯ドラマで共演することになった新人女優Uの言動に面食らっていました。
「まるで違う動物のようだ。会話が最後まで成立しない…」
Uは17歳。当時、W芸能事務所に所属していました。
W社は業界事務所としては、失礼ながら、弱小の部類に区分けされる存在で、モデル事業部が主体でした。Uも当初はモデルを目指していたようですが、やはり俳優への憧れが強く、地道に俳優オーディションをコツコツと受けては配役=仕事を獲得していました。
その時も公共放送の朝の連続帯ドラマのヒロインオーディションを受けたものの次点に終わっていました。
が、それでも主人公の姉妹役を勝ち取っていました。
そのドラマでU達の父親役を務めたのがKでした。
この多少天然がかった天真爛漫そのもののUの、しかし、その演技における底知れぬ天賦の才を、Kは見逃がしませんでした。
実際、その時、Uは人気映画監督がメガホンをとるマル秘プロジェクト~落ちこぼれ高校生達がビッグバンド結成に奮闘する青春映画のオーディションでみごと主役の座を射止めていたのです。
Kは自分の所属する大手芸能事務所Aのトップに、彼女は強力なバックアップ体制があれば、必ず頭角を顕す逸材だとUの引抜を強く進言したのです。
A社は当時、圧倒的人気を誇るロック・バンドをはじめ、多くの人気俳優・歌手を擁し、破竹の勢いで業容を拡大中であり、先日、IPO(株式公開)も果たしたばかりでした。
A社は直ちにUに移籍を働きかけます。
しかし、業界トップスラスの大手事務所からの勧誘にも拘わらず、Uの反応は大方の予想に反したものでした。
「自分をこれまで育ててくれた今の事務所を裏切ることは出来ない」と。
Uは頑なでした。
UがW社に入社したのは3年前。W社との契約は通算20年まで更新が可能となっていたようです。
もともとW社は、約20年前、O社長が、俳優を目指す友人をバックアップすべく設計会社を脱サラして創業した会社でした。事務所はその後モデル事業部を新設し、モデル事業に注力していくのは前記のとおりです。
一方、Uを獲得すると決めたA社のトップの決断は迅速で大胆でした。
A社はUでなく、当時のO社長に直接働きかけ、ある提案をします。
ーなんと、A社はUを手に入れる為、W社を会社丸ごと買収≒会社丸ごと移籍案を申し出たのです。
これにより、UはW社との関係を引き続き維持しつつ、自動的にA社所属のタレントとなったのです。
因みに、W社は現在もA社の一部門として存続しています。
また、O氏は新人発掘の才がある敏腕スカウトマンとして業界では知られており、今もA社の新人開発室にマネージャーとして所属し、多くの有能なタレントを発掘し続けています。
A社所属となったUは、すぐに、クラシック音楽をテーマにした人気漫画を原作とする「月9ドラマ」(自他共に認める某放送局の看板ドラマ枠)の主演に抜擢されます。
当時を回顧してO氏はこうコメントしています。
「(Uが)グングン面白いように伸びていく訳です。『何で?』って思うくらい。おっきい会社に入ると全然違うと思いましたね」
当該番組は好評を博し、視聴率も20%超えを記録、続編も作成され、遂には映画化され、やはり大ヒットします。
Uは一躍、大ブレイクを果たしたのです。
その後も公共放送の日曜日の年間ドラマの主演も務め、数々の演技関係の賞も受賞、若手実力俳優として不動の地位を築きあげ今日に至っています。
数年前、W社との最初の所属契約から数えて通算20年の契約期間満了に伴い、UはA社から独立し、個人事務所を開業します。独立に関する両者のコメントを見る限り、円満に退社出来たようです。
さて、U一人を手に入れる為にW社を会社ごと買うと言う思い切った手を打ったA社でしたが、このM&Aには想定外の「お釣り」(おまけ?)もありました。
W社にはUの他、当時も数名のタレントが所属していました。その中の一人に、やはりO氏が、(かの有名な、伝説?の、あの「スカウトの聖地」と呼ばれることもある)原宿の「竹下通」でスカウトしたYがいました。
A社による買収後、Yも先に言及した朝の連続帯ドラマや日曜の年間ドラマで主役を務め、やはり実力俳優としてブレイクします。公共放送の年末恒例の歌番組の司会も務め、数多くのCMに出演、A社の収益に大きく貢献することとなったのです。
この時のM&Aの譲渡価格は未公表ですが、その後の2人の活躍を考えれば、A社は十分に投資資金は回収出来たものと思われます。
その日、個性派俳優として知られるKは、公共放送の朝の帯ドラマで共演することになった新人女優Uの言動に面食らっていました。
「まるで違う動物のようだ。会話が最後まで成立しない…」
Uは17歳。当時、W芸能事務所に所属していました。
W社は業界事務所としては、失礼ながら、弱小の部類に区分けされる存在で、モデル事業部が主体でした。Uも当初はモデルを目指していたようですが、やはり俳優への憧れが強く、地道に俳優オーディションをコツコツと受けては配役=仕事を獲得していました。
その時も公共放送の朝の連続帯ドラマのヒロインオーディションを受けたものの次点に終わっていました。
が、それでも主人公の姉妹役を勝ち取っていました。
そのドラマでU達の父親役を務めたのがKでした。
この多少天然がかった天真爛漫そのもののUの、しかし、その演技における底知れぬ天賦の才を、Kは見逃がしませんでした。
実際、その時、Uは人気映画監督がメガホンをとるマル秘プロジェクト~落ちこぼれ高校生達がビッグバンド結成に奮闘する青春映画のオーディションでみごと主役の座を射止めていたのです。
Kは自分の所属する大手芸能事務所Aのトップに、彼女は強力なバックアップ体制があれば、必ず頭角を顕す逸材だとUの引抜を強く進言したのです。
A社は当時、圧倒的人気を誇るロック・バンドをはじめ、多くの人気俳優・歌手を擁し、破竹の勢いで業容を拡大中であり、先日、IPO(株式公開)も果たしたばかりでした。
A社は直ちにUに移籍を働きかけます。
しかし、業界トップスラスの大手事務所からの勧誘にも拘わらず、Uの反応は大方の予想に反したものでした。
「自分をこれまで育ててくれた今の事務所を裏切ることは出来ない」と。
Uは頑なでした。
UがW社に入社したのは3年前。W社との契約は通算20年まで更新が可能となっていたようです。
もともとW社は、約20年前、O社長が、俳優を目指す友人をバックアップすべく設計会社を脱サラして創業した会社でした。事務所はその後モデル事業部を新設し、モデル事業に注力していくのは前記のとおりです。
一方、Uを獲得すると決めたA社のトップの決断は迅速で大胆でした。
A社はUでなく、当時のO社長に直接働きかけ、ある提案をします。
ーなんと、A社はUを手に入れる為、W社を会社丸ごと買収≒会社丸ごと移籍案を申し出たのです。
これにより、UはW社との関係を引き続き維持しつつ、自動的にA社所属のタレントとなったのです。
因みに、W社は現在もA社の一部門として存続しています。
また、O氏は新人発掘の才がある敏腕スカウトマンとして業界では知られており、今もA社の新人開発室にマネージャーとして所属し、多くの有能なタレントを発掘し続けています。
A社所属となったUは、すぐに、クラシック音楽をテーマにした人気漫画を原作とする「月9ドラマ」(自他共に認める某放送局の看板ドラマ枠)の主演に抜擢されます。
当時を回顧してO氏はこうコメントしています。
「(Uが)グングン面白いように伸びていく訳です。『何で?』って思うくらい。おっきい会社に入ると全然違うと思いましたね」
当該番組は好評を博し、視聴率も20%超えを記録、続編も作成され、遂には映画化され、やはり大ヒットします。
Uは一躍、大ブレイクを果たしたのです。
その後も公共放送の日曜日の年間ドラマの主演も務め、数々の演技関係の賞も受賞、若手実力俳優として不動の地位を築きあげ今日に至っています。
数年前、W社との最初の所属契約から数えて通算20年の契約期間満了に伴い、UはA社から独立し、個人事務所を開業します。独立に関する両者のコメントを見る限り、円満に退社出来たようです。
さて、U一人を手に入れる為にW社を会社ごと買うと言う思い切った手を打ったA社でしたが、このM&Aには想定外の「お釣り」(おまけ?)もありました。
W社にはUの他、当時も数名のタレントが所属していました。その中の一人に、やはりO氏が、(かの有名な、伝説?の、あの「スカウトの聖地」と呼ばれることもある)原宿の「竹下通」でスカウトしたYがいました。
A社による買収後、Yも先に言及した朝の連続帯ドラマや日曜の年間ドラマで主役を務め、やはり実力俳優としてブレイクします。公共放送の年末恒例の歌番組の司会も務め、数多くのCMに出演、A社の収益に大きく貢献することとなったのです。
この時のM&Aの譲渡価格は未公表ですが、その後の2人の活躍を考えれば、A社は十分に投資資金は回収出来たものと思われます。
スモールM&Aが指し示す未来 ~ 企業の流動化
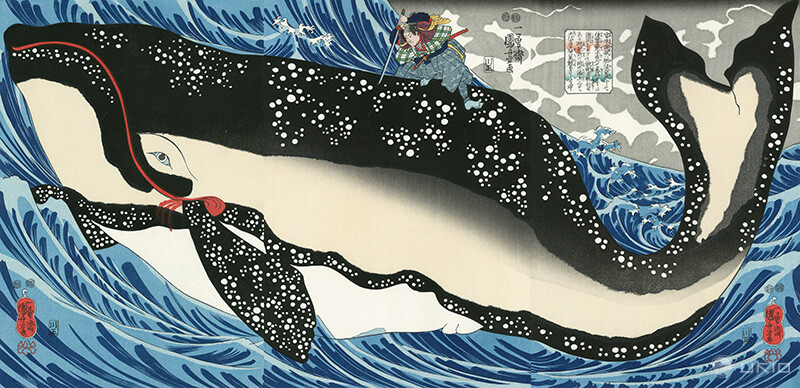
そもそも、このM&Aはスモール?
上のA社によるW社のM&A~吸収合併は「事実」には違いありませんが、具体的スキーム、金額等となると、当時のA社の開示情報・有価証券報告書等でも殆ど触れられておらず、当該年度前後の勘定科目の差異から痕跡を探ろうとトライしましたが、流石に大手事務所の為、他の取引も多く、特定することは困難でした。
したがって、本件が金額的にスモールM&Aに該当するか否かは断定出来ませんが、客観的に見て、いかに将来輝くこととなる複数の原石を有していたとしても当時の株価算定上はそれらを織り込んだ高額評価になることは常識的には考え難いと思われます。
とまれ、このM&Aが示したものは、最早M&Aは買収する側もされる側も共に社運を賭けた一大プロジェクト…等では全くなく、特定の経営上の課題(テーマ)解決の為の一手段に過ぎないと言うことでした。
(売り手のO氏だけは「身分」が変わりましたが、W社の他の関係者の仕事・業務は殆ど変わることはなく、O氏も自分の天職ともいうべき仕事を続けられているようですし…)
本件は言ってみれば、たまたま、経営上のテーマが「特定の人物を引き抜く」ことで、その代替手段として「その人物が所属する企業を買収」しただけです。
勿論、買収後に当該人物に退社されては元も子もありませんので、そこは事前に契約内容で色々縛りを設けた筈です。
形式的なM&A、目的を特定したM&Aが着目され、更にスモール化したことで、より普遍化し、より手軽な、より使い易い経営上の便利なツールとなっていくのです。
一発勝負で何もかも達成・実現することを目指すのではなく、スモールなるが故に小刻みに様子を見ながら~適宜、軌道修正もしながら~必要に応じて、何回も売ったり買ったりすることが可能となります。
勿論、従来も、買収した結果としてくっ付いてきた部分で不要な部分が出てくれば、また売却する等の対処はしていましたが。
スモール化はこれらの(ムダな)要素もスモール化していきます。
この「ツール」の具体的な用途としては
例えば---
特定の人材を傘下に置く為、
特定の不動産を手に入れる為、
特定の技術を入手する為、
特定の資格を手中にする為、
特定の市場を押さえる為、
特定の仕入れ・外注ルートを確保する為、
特定の顧客を囲い込む為、
特定の分野への進出の為、
あるいは
特定の事業、市場、分野から撤退する為
…
用途はまだまだあるでしょう。
そして、譲渡金額が少額化することによりM&Aのリスクも相対的に低下します。
そうなると--
➡ 手数料(含む「ミニマムチャージ」)も相対的に少額化し、買い手は更に買い易くなる
➡ 買う為の障壁が下がることで=手を出し易くなることで、参加者の裾野が更に拡大する
企業規模に拘わらず、あらゆる業種、分野、産業区分を問わずM&Aが広がる
⇛ この結果、広義の個人起業家を含め、新たな経営者が続々登場し、
経営者層全般に変化・意識改革が起きる。
➡ M&A少額化/普及と共に企業経営のツールとしてのM&A活用の認知が格段に広がる。
⇛ この結果、従来、ともすれば固定的・硬直的だった下記の企業経営上の諸要素と
言われていたもの自体の流動化が進展する。
・業種/市場/分野/経営主体・経営者/顧客/取扱い製品・商品・サービス/仕入・外注ルート/従業員 …
こうして、経営の主体の流動化はもとより、企業自体が、時の環境及び自己の置かれた位置を認識したうえで、M&Aを活用することで、大胆に自己の「強み」を伸ばし、「弱み」を克服あるいは押さえること=「企業要素の柔軟化/流動化」が(スモール)容易に実現することが可能になろうとしているのです。
わが社は、こういう企業ですーーもはや、自社の紹介は永遠不滅のものでなく、
翌年には、当該企業は別のものになっているかも知れません。そして、それは決して悪いことではありません。
現代の進化論によると、いくつも偶然に発生する突然変異(進化)したものの中で、たまたま環境に適合した種が生き延びる=進化することになる、となっているようですが、この論理をスモールM&Aに当てはめてみましょう。
スモールM&Aの登場により、企業は自らの種の基本的属性=企業の諸要素(前記したもの)すらも自らの
意思で(相手さえ見付けられれば)自由に取捨選択≒生き延びる為の突然変異を起こすことが可能となったと私は認識しています。
つまり、企業が生き残る為の「突然変異」を人為的に起こすツール、それこそが(スモール)M&Aだと思うのです。
これらは一つ一つは、個社単位の出来事に過ぎないのですが、しかしM&Aのスモール化により、より多くの企業の行動の結果として前記のような流動化が、至る所で、同時多発的併行的に、起こり得る可能性を秘めています。
つまり、そのような社会・時代が、もう直ぐそこまで近づいている、と感じるのは、私だけでしょうか?
上のA社によるW社のM&A~吸収合併は「事実」には違いありませんが、具体的スキーム、金額等となると、当時のA社の開示情報・有価証券報告書等でも殆ど触れられておらず、当該年度前後の勘定科目の差異から痕跡を探ろうとトライしましたが、流石に大手事務所の為、他の取引も多く、特定することは困難でした。
したがって、本件が金額的にスモールM&Aに該当するか否かは断定出来ませんが、客観的に見て、いかに将来輝くこととなる複数の原石を有していたとしても当時の株価算定上はそれらを織り込んだ高額評価になることは常識的には考え難いと思われます。
とまれ、このM&Aが示したものは、最早M&Aは買収する側もされる側も共に社運を賭けた一大プロジェクト…等では全くなく、特定の経営上の課題(テーマ)解決の為の一手段に過ぎないと言うことでした。
(売り手のO氏だけは「身分」が変わりましたが、W社の他の関係者の仕事・業務は殆ど変わることはなく、O氏も自分の天職ともいうべき仕事を続けられているようですし…)
本件は言ってみれば、たまたま、経営上のテーマが「特定の人物を引き抜く」ことで、その代替手段として「その人物が所属する企業を買収」しただけです。
勿論、買収後に当該人物に退社されては元も子もありませんので、そこは事前に契約内容で色々縛りを設けた筈です。
形式的なM&A、目的を特定したM&Aが着目され、更にスモール化したことで、より普遍化し、より手軽な、より使い易い経営上の便利なツールとなっていくのです。
一発勝負で何もかも達成・実現することを目指すのではなく、スモールなるが故に小刻みに様子を見ながら~適宜、軌道修正もしながら~必要に応じて、何回も売ったり買ったりすることが可能となります。
勿論、従来も、買収した結果としてくっ付いてきた部分で不要な部分が出てくれば、また売却する等の対処はしていましたが。
スモール化はこれらの(ムダな)要素もスモール化していきます。
この「ツール」の具体的な用途としては
例えば---
特定の人材を傘下に置く為、
特定の不動産を手に入れる為、
特定の技術を入手する為、
特定の資格を手中にする為、
特定の市場を押さえる為、
特定の仕入れ・外注ルートを確保する為、
特定の顧客を囲い込む為、
特定の分野への進出の為、
あるいは
特定の事業、市場、分野から撤退する為
…
用途はまだまだあるでしょう。
そして、譲渡金額が少額化することによりM&Aのリスクも相対的に低下します。
そうなると--
➡ 手数料(含む「ミニマムチャージ」)も相対的に少額化し、買い手は更に買い易くなる
➡ 買う為の障壁が下がることで=手を出し易くなることで、参加者の裾野が更に拡大する
企業規模に拘わらず、あらゆる業種、分野、産業区分を問わずM&Aが広がる
⇛ この結果、広義の個人起業家を含め、新たな経営者が続々登場し、
経営者層全般に変化・意識改革が起きる。
➡ M&A少額化/普及と共に企業経営のツールとしてのM&A活用の認知が格段に広がる。
⇛ この結果、従来、ともすれば固定的・硬直的だった下記の企業経営上の諸要素と
言われていたもの自体の流動化が進展する。
・業種/市場/分野/経営主体・経営者/顧客/取扱い製品・商品・サービス/仕入・外注ルート/従業員 …
こうして、経営の主体の流動化はもとより、企業自体が、時の環境及び自己の置かれた位置を認識したうえで、M&Aを活用することで、大胆に自己の「強み」を伸ばし、「弱み」を克服あるいは押さえること=「企業要素の柔軟化/流動化」が(スモール)容易に実現することが可能になろうとしているのです。
わが社は、こういう企業ですーーもはや、自社の紹介は永遠不滅のものでなく、
翌年には、当該企業は別のものになっているかも知れません。そして、それは決して悪いことではありません。
現代の進化論によると、いくつも偶然に発生する突然変異(進化)したものの中で、たまたま環境に適合した種が生き延びる=進化することになる、となっているようですが、この論理をスモールM&Aに当てはめてみましょう。
スモールM&Aの登場により、企業は自らの種の基本的属性=企業の諸要素(前記したもの)すらも自らの
意思で(相手さえ見付けられれば)自由に取捨選択≒生き延びる為の突然変異を起こすことが可能となったと私は認識しています。
つまり、企業が生き残る為の「突然変異」を人為的に起こすツール、それこそが(スモール)M&Aだと思うのです。
これらは一つ一つは、個社単位の出来事に過ぎないのですが、しかしM&Aのスモール化により、より多くの企業の行動の結果として前記のような流動化が、至る所で、同時多発的併行的に、起こり得る可能性を秘めています。
つまり、そのような社会・時代が、もう直ぐそこまで近づいている、と感じるのは、私だけでしょうか?