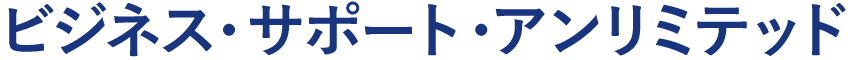お陰様で、吸血型M&A(M&Aスキームを悪用した詐欺まがいのトラブル案件)については、皆様の関心も高いようで、色々なお声もうけたまわっております。
今回は、その続編です。内容は下記。
・不適切な買主の見分け方、未然に防ぐ方法
・仲介/FA事業者は、何に注目して選ぶか?
不適切な買主の見分け方
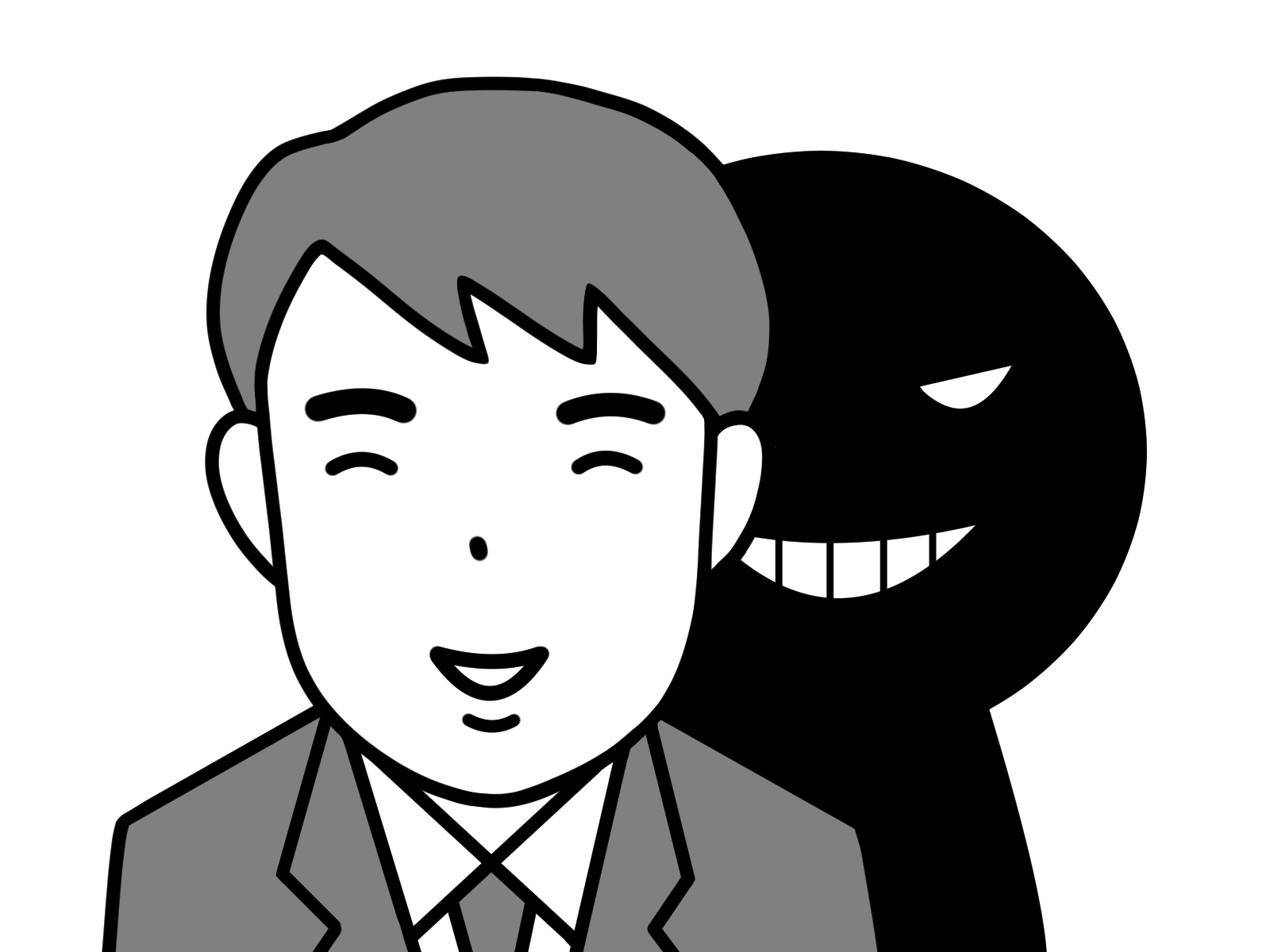
「不適切な買主」とは、ここでは、一連の吸血型M&Aの買い手(譲受側)及び、それに類する輩を指します。
ここを見分けることはM&A上の最重要事項で、売主としては、決して仲介/FA業者に任せることなく、自分で判断しなければならないところだと私は考えています。
具体的には、仲介/FA業者に「買主」に関して、次のような確認を要求すべきです。
1.「特定事業者リスト」等、この種の不芳先な買主についての情報をどのような方法で収集しているか?
その情報源の信憑性はどのように担保されているか?
その情報源では、今回の相手(買いの希望者)は、どう判定されているか?
2.書類・データ上の調査は当然として、相手の事業の実態をどのように確認したのか?
現地訪問、生産物・商品・成果物の現物確認 等 …本当にやってる?
1については「(一社)M&A支援機関協会」の会員であれば、所定の手続きを踏むことで、各会員から集められた過去の不適切な事例の企業のデータである「特定事業者リスト」にアクセスすることが出来ます。(下記リンク頁参照)
国内の有力M&A支援事業者の殆どが加入していますので、データの質と量はそれなりに整備されていると考えられます。
2について、従来、売主が買主に決算内容の開示を求めるなど「あり得ない」と言う風潮も業界の一部にはありましたが、今や、例の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、要請することが推奨されております。
最低限度の確認として、今回の買取資金の手当て(例:手元現金、資産売却、銀行等からの借入金 等)は、どのようになっているか、どこまで進んでいるかについては、必ず確認すべきと考えています。
これらに強い抵抗を示す買主は疑ってかかる方が無難です。あとで後悔しない為にも。
データ的にも買い手候補は他にも沢山いるのですから。
ここを見分けることはM&A上の最重要事項で、売主としては、決して仲介/FA業者に任せることなく、自分で判断しなければならないところだと私は考えています。
具体的には、仲介/FA業者に「買主」に関して、次のような確認を要求すべきです。
1.「特定事業者リスト」等、この種の不芳先な買主についての情報をどのような方法で収集しているか?
その情報源の信憑性はどのように担保されているか?
その情報源では、今回の相手(買いの希望者)は、どう判定されているか?
2.書類・データ上の調査は当然として、相手の事業の実態をどのように確認したのか?
現地訪問、生産物・商品・成果物の現物確認 等 …本当にやってる?
1については「(一社)M&A支援機関協会」の会員であれば、所定の手続きを踏むことで、各会員から集められた過去の不適切な事例の企業のデータである「特定事業者リスト」にアクセスすることが出来ます。(下記リンク頁参照)
国内の有力M&A支援事業者の殆どが加入していますので、データの質と量はそれなりに整備されていると考えられます。
2について、従来、売主が買主に決算内容の開示を求めるなど「あり得ない」と言う風潮も業界の一部にはありましたが、今や、例の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、要請することが推奨されております。
最低限度の確認として、今回の買取資金の手当て(例:手元現金、資産売却、銀行等からの借入金 等)は、どのようになっているか、どこまで進んでいるかについては、必ず確認すべきと考えています。
これらに強い抵抗を示す買主は疑ってかかる方が無難です。あとで後悔しない為にも。
データ的にも買い手候補は他にも沢山いるのですから。
仲介/FA業者の「体質」の見分け方
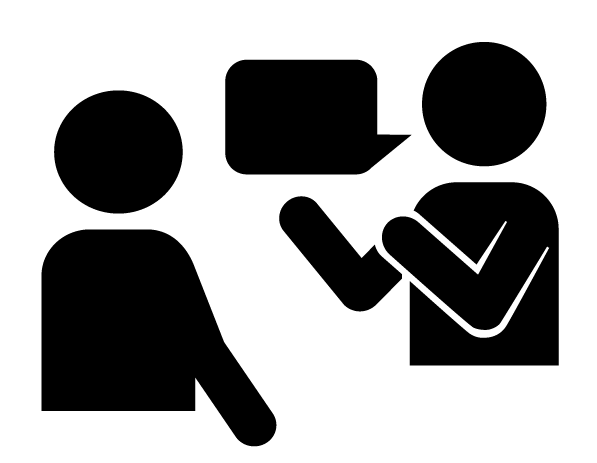
仲介/FA業者の選び方については、まず、上記の買主に対する「確認」要求に対して、真摯に対応しているかどうかで自ずと答えが出ると考えます。
それに加え、これから、私の独断と偏見を申し上げます。
最初にお断りすべきは、既に何度か、本ブログでも触れました、斯業界の体質・風土があります。
勿論、参加者全員がそうだと言う訳ではありませんが、譬え、業界の一部の不心得者の仕業であったとしても、今回のルシアン事件他で明らかになったように、少なからぬ数の不芳事例が起きたことと、そこに共通する業界風土が厳然として存在していたと言うことです。
以下に列記します。
1.まず、中小M&Aの8割を占める「仲介」は利益相反の温床であること。
業界の有力企業等がこれについて色々反論していますが、常識で考えて、双方の代理的立場が利益相反行為に結び付きやすいことは容易に想定されます。
弁護士は同じ事務所内では(担当弁護士が異なっても)相対する案件依頼は受けません。銀行も対立する双方の顧客に資金を融通することは避けます。
現に、中企庁も「ガイドライン(第3版)」で警鐘をならしてしています。
2.次に、当該支援機関の中で、過度なインセンティブ報酬制度を実施している先があるのではないか?
インセンティブ自体に罪はありません。
問題は、その運用の仕方です。
「低給与+高インセンティブ」の報酬体系が、これらの問題の根つ子にあるのではないか? と言う問題提起でもあります。
因みに、業界では、1億円を稼ぐ猛者もいると噂されます。
一方、正確な統計はありませんが、レコフ等が公表しているM&A件数と、中企庁に登録しているM&A支援機関の専従者数から推測すれば、おそらく専従者が年間成約し得るM&Aは、せいぜい1件、多くて2件程度と言う情況が大半であると逆算出来ます。
そうであるとするならば、彼ら専従者は、折角手に入れた年に1度程度しかないチャンスを、「高インセンティブ」欲しさに、何が何でも逃すまい、と必死に成約させようと動くのは火を見るより明らかでしょう。
その際、ひょっとすると、「この買主はヤバイ先かも知れないな」と思っていても、顧客(売主)の利益より、自社=自分の利益の為に、おくびにも出さず、目を瞑ってしまうかも知れません。
それが、今回の一連の事件の大きな要因の一つだと私は考えています。
解決策/予防策は簡単です。
当該M&Aに関する全ての情報を一人の担当者に独占させないよう、全社的に特にコンプラ部門に登録させ、必ずペアで対応させる等一人の担当者が独断先行しないよう相互牽制(チェック&バランス)の仕組みを社内で構築することです。そういう仕組みになっているのかを質問すれば、任せてよい支援機関かどうかの判断も容易になると思われます。
3.「当社の報酬は成功報酬のみです」の罠
一見、顧客指向で結構なことのように聞こえますね。現在、殆どの大手が、そう宣伝しています。
しかし、果たして、それは真に顧客本位を実現するものなのでしょうか?
相手の企業を調査するには費用も手間もかかるのは自明の理です。
その請求を敢えて行わないと言うのは勿論、顧客受けを狙う、営業戦略上の選択肢の一つです。
が、上の例で挙げた様に、その担当者にとって、年に一度のチャンスとすれば、「ちょっと、マズイかな」と思っていても、敢えて顧客には謂わず、
むしろ「いや、これは絶対お勧めですよ。この機会を逃すと、もう2度と、こんな良い条件の買主は現れないかも知れませんよ」と、貴方に成約を迫ることが十分あり得るとは思いませんか?
皆さまも、いろいろな人生経験を経てこられて、「世の中、善人ばかりではない」ことも「人間も弱い生き物で、目の前の誘惑につい…」と言うところがあることは、先刻ご存知でしょう。
私たちは、M&A金額にもよりますが、契約時点で原則15万円程度の着手金をいただいております。
このお金をいただくことで、「ヤバいな」と判断した案件には躊躇なく~多額の成功報酬の誘惑に後ろ髪ひかれることなく、
「この案件は以下の理由で”No!”です」と言えるのです。(当然ながら、最終判断はお客様が下します)
これが「成功報酬オンリー」だけの報酬体系ですと、そうはいきません。何が何でも、掛かった費用を取り戻そうと、先に挙げたような行動に出ることを否定出来ません。
おそらく、都合100件近くに及んだルシアン+類似案件も、そうした業界体質から生まれたと私は見ています。
わずか数十万円をケチって、数千万円の預金を奪われ、挙句に倒産の憂き目を見る。
「安物買いの銭失い」そのものではないでしょうか?
目の前にぶら下がるウマイ話に乗せられないでください。
私たちは少数派ですが、きちんと着手金≒必要調査資金をいただき、真にお客様のベネフィットとなる案件を見出してまいります。
どうぞ、よろしくお願いします。
それに加え、これから、私の独断と偏見を申し上げます。
最初にお断りすべきは、既に何度か、本ブログでも触れました、斯業界の体質・風土があります。
勿論、参加者全員がそうだと言う訳ではありませんが、譬え、業界の一部の不心得者の仕業であったとしても、今回のルシアン事件他で明らかになったように、少なからぬ数の不芳事例が起きたことと、そこに共通する業界風土が厳然として存在していたと言うことです。
以下に列記します。
1.まず、中小M&Aの8割を占める「仲介」は利益相反の温床であること。
業界の有力企業等がこれについて色々反論していますが、常識で考えて、双方の代理的立場が利益相反行為に結び付きやすいことは容易に想定されます。
弁護士は同じ事務所内では(担当弁護士が異なっても)相対する案件依頼は受けません。銀行も対立する双方の顧客に資金を融通することは避けます。
現に、中企庁も「ガイドライン(第3版)」で警鐘をならしてしています。
2.次に、当該支援機関の中で、過度なインセンティブ報酬制度を実施している先があるのではないか?
インセンティブ自体に罪はありません。
問題は、その運用の仕方です。
「低給与+高インセンティブ」の報酬体系が、これらの問題の根つ子にあるのではないか? と言う問題提起でもあります。
因みに、業界では、1億円を稼ぐ猛者もいると噂されます。
一方、正確な統計はありませんが、レコフ等が公表しているM&A件数と、中企庁に登録しているM&A支援機関の専従者数から推測すれば、おそらく専従者が年間成約し得るM&Aは、せいぜい1件、多くて2件程度と言う情況が大半であると逆算出来ます。
そうであるとするならば、彼ら専従者は、折角手に入れた年に1度程度しかないチャンスを、「高インセンティブ」欲しさに、何が何でも逃すまい、と必死に成約させようと動くのは火を見るより明らかでしょう。
その際、ひょっとすると、「この買主はヤバイ先かも知れないな」と思っていても、顧客(売主)の利益より、自社=自分の利益の為に、おくびにも出さず、目を瞑ってしまうかも知れません。
それが、今回の一連の事件の大きな要因の一つだと私は考えています。
解決策/予防策は簡単です。
当該M&Aに関する全ての情報を一人の担当者に独占させないよう、全社的に特にコンプラ部門に登録させ、必ずペアで対応させる等一人の担当者が独断先行しないよう相互牽制(チェック&バランス)の仕組みを社内で構築することです。そういう仕組みになっているのかを質問すれば、任せてよい支援機関かどうかの判断も容易になると思われます。
3.「当社の報酬は成功報酬のみです」の罠
一見、顧客指向で結構なことのように聞こえますね。現在、殆どの大手が、そう宣伝しています。
しかし、果たして、それは真に顧客本位を実現するものなのでしょうか?
相手の企業を調査するには費用も手間もかかるのは自明の理です。
その請求を敢えて行わないと言うのは勿論、顧客受けを狙う、営業戦略上の選択肢の一つです。
が、上の例で挙げた様に、その担当者にとって、年に一度のチャンスとすれば、「ちょっと、マズイかな」と思っていても、敢えて顧客には謂わず、
むしろ「いや、これは絶対お勧めですよ。この機会を逃すと、もう2度と、こんな良い条件の買主は現れないかも知れませんよ」と、貴方に成約を迫ることが十分あり得るとは思いませんか?
皆さまも、いろいろな人生経験を経てこられて、「世の中、善人ばかりではない」ことも「人間も弱い生き物で、目の前の誘惑につい…」と言うところがあることは、先刻ご存知でしょう。
私たちは、M&A金額にもよりますが、契約時点で原則15万円程度の着手金をいただいております。
このお金をいただくことで、「ヤバいな」と判断した案件には躊躇なく~多額の成功報酬の誘惑に後ろ髪ひかれることなく、
「この案件は以下の理由で”No!”です」と言えるのです。(当然ながら、最終判断はお客様が下します)
これが「成功報酬オンリー」だけの報酬体系ですと、そうはいきません。何が何でも、掛かった費用を取り戻そうと、先に挙げたような行動に出ることを否定出来ません。
おそらく、都合100件近くに及んだルシアン+類似案件も、そうした業界体質から生まれたと私は見ています。
わずか数十万円をケチって、数千万円の預金を奪われ、挙句に倒産の憂き目を見る。
「安物買いの銭失い」そのものではないでしょうか?
目の前にぶら下がるウマイ話に乗せられないでください。
私たちは少数派ですが、きちんと着手金≒必要調査資金をいただき、真にお客様のベネフィットとなる案件を見出してまいります。
どうぞ、よろしくお願いします。