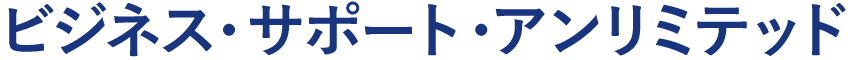サブタイトルは、江戸時代の大名にして、剣豪、そして名エッセイストとしても著名な松浦静山(本名:松浦清)が、その著「常静子剣談」の中で述べた言葉です。
折角、幾多の困難・障壁・難題を乗り越えて漕ぎつけたM&Aが結果的に失敗、あるいは、M&Aの交渉自体が破談に至るのは、そこに明確な失敗事由~静山によれば、「道(≒法則)に背き、術(≒技術)を違え」ていること~が存在しているからとなります。
いくら成功事例を集めて分析しても、成功の要素を特定するのは難しく、且つ、中には単なるラッキーもあるでしょう。むしろ、失敗事例にて失敗の要因をしっかり押さえて≒留意して、当初から適切に対応・進めていく、あるいは固有の問題点を事前に除去していけば、当該案件が失敗する懸念は相対的に少なくなると言うことは言えます。
特に、スモールM&Aは、詰めるべき部分が相対的に少ないので、的を絞ってアプローチすることにより、失敗しないM&A≒成功するM&Aの確率は格段に高まる筈です。
今回は、今やスモールM&Aの一大勢力になりつつある「個人」(サラリーマン)が、M&Aを活用して買収=起業する際に、交渉段階における留意点を見て行きましょう。
事例: 売り手とは合意したのに

事例➃
花卉販売(花屋) 事業譲渡 (個人事業)
希望価格 50万円
売上 数千万円 営業利益/EBITDA 僅かにプラス
借入 なし
譲渡事由:経営者引退(体調不良)
背景~D社長の事情
D社長は20年あまり東京23区内のJR駅近くで花屋を個人営業していました。
この間、入居していた店舗は周囲の大規模開発が進む中でビルの一角となり、周囲はすっかりオフィス街となりました。その法人需要に支えられ、業績は堅調でしたが、最近、D社長は体調を壊し、店を畳むことにし、関係者への連絡をとり始めました。
その中で、懇意にしている法人顧客の担当者から、「廃業するにもカネがかかる。買取ってもらってはどうか?」として、M&Aのマッチングサイトを紹介されました。
一方、流企業に勤めるα氏は、従来から副業をこなしている中、新たなビジネスを求め、丁度当該マッチングサイトに登録したところでした。
早速、立候補したα氏とD社長は直ぐに意気投合し、話はとんとん拍子に進みました。
しかし、意外な盲点があり、この案件は破談となりました。
失敗の要因:
1.資金調達の計画が狂った。
2.サラリーマンの起業に対する世間の許容度・信頼感は、まだまだ低く、風当たりは強いものでした。
花卉販売(花屋) 事業譲渡 (個人事業)
希望価格 50万円
売上 数千万円 営業利益/EBITDA 僅かにプラス
借入 なし
譲渡事由:経営者引退(体調不良)
背景~D社長の事情
D社長は20年あまり東京23区内のJR駅近くで花屋を個人営業していました。
この間、入居していた店舗は周囲の大規模開発が進む中でビルの一角となり、周囲はすっかりオフィス街となりました。その法人需要に支えられ、業績は堅調でしたが、最近、D社長は体調を壊し、店を畳むことにし、関係者への連絡をとり始めました。
その中で、懇意にしている法人顧客の担当者から、「廃業するにもカネがかかる。買取ってもらってはどうか?」として、M&Aのマッチングサイトを紹介されました。
一方、流企業に勤めるα氏は、従来から副業をこなしている中、新たなビジネスを求め、丁度当該マッチングサイトに登録したところでした。
早速、立候補したα氏とD社長は直ぐに意気投合し、話はとんとん拍子に進みました。
しかし、意外な盲点があり、この案件は破談となりました。
失敗の要因:
1.資金調達の計画が狂った。
2.サラリーマンの起業に対する世間の許容度・信頼感は、まだまだ低く、風当たりは強いものでした。
個人がM&A(買)を行う際の留意点

1.買収には、まず資金が必要
当然ですね。まずは買収資金。そして、それに付随する諸資金~特に支援者の報酬もお忘れずに…
まあ、それはそれとして、企業を運営すれば、所謂「運転資金」が発生します。
従業員の給与類を筆頭に、業種・企業特有の必要資金があります。
何と謂っても、事業所費用。所謂、毎月の家賃の他に敷金/保証金の類の資金手当が必要です。
当該物件が買収対象に含まれていれば、まだしも、(スモールM&Aの場合の多くは、含まれていません)
そうでなければ、家主(売り手の場合もあります)との賃貸契約から巻き直す必要があります。
2.事業承継は多くの再契約が必要になります。
次に(スモールM&Aの大半を占める)事業承継の場合には、企業買収と異なり、改めて雇用関係を含め、関係当事者の再契約・合意・同意・理解等そして当局の許認可等が必要です。
タイミングは難しいのですが、小売等不特定多数の顧客相手の商売は別として、どこかの段階で、大口の販売先(顧客)の理解を得ないことには、買収後の円滑な取引に支障が出かねません。(この点は、企業買収も基本は同じです)
仕入先や先に挙げた家主との関係も同様です。
今回のケースでは、α氏は両方で苦労しました。
α氏は実は既に副業を3年前からやっており、経営実績は事業承継関係補助金等申請に有利だと聴いていました。
ところが、良く調べると、個人は5年、法人で3年以上の経営実績(エビデンスとして各決算書が必要)が必要でした。(2024年4月現在。今後の公募の際に変更される可能性はあります。後記参照)
期待してしていた補助金での資金調達が出来なかったα氏ですが、その後各金融機関に打診し、辛うじて日本政策金融公庫から借り入れることが出来、ほっと一息つくことが出来ました。
しかし、α氏に次なる難問が降りかかってきました。
継承予定の花屋は、前記のとおり、数年前の大規模開発されたオフィスビルの中にありました。まさに一等地です。以前から、ビル敷地で商売していたD社長は優先的に入居が認められていたのです。大家は上場企業の大手デベロッパーの関係会社でした。
D社長とα氏が事業引継ぎの挨拶を兼ね、入居申込に行った際も大家企業の担当者は丁寧で親身になって手続きをしてくれました。ただ、提示された家賃額はD社長が払っている金額の数倍になっていました。
そして、数日後もたらされた入居審査結果は、「入居者としての基準を満たしていない」と謂う結論でした。
既存事業の実績規模や法人でないことも理由のようでしたが、詳細は開示されませんでした。
当該花屋の顧客の殆どは、このビルに入居している企業です。
慌てて、今や殆どビル街となってしまった、その街のビル群の中での入居可能場所を手当たり次第に当たりました。しかし、花屋の営業が出来そうな空きスペース、物件もなく、あっても更に高価な家賃~とても商売としてはペイ出来ない程度の金額提示を受けました。
ついに、ここに至って、α氏もM&Aを断念。D社長も結局廃業する他ありませんでした。
註:本件は私の周辺で実際に起こった事実に基づいて執筆しておりますが、守秘義務の観点から、基本的テーマに関係ない部分、一部の詳細・ディテールについては適宜修正を加えております。
当然ですね。まずは買収資金。そして、それに付随する諸資金~特に支援者の報酬もお忘れずに…
まあ、それはそれとして、企業を運営すれば、所謂「運転資金」が発生します。
従業員の給与類を筆頭に、業種・企業特有の必要資金があります。
何と謂っても、事業所費用。所謂、毎月の家賃の他に敷金/保証金の類の資金手当が必要です。
当該物件が買収対象に含まれていれば、まだしも、(スモールM&Aの場合の多くは、含まれていません)
そうでなければ、家主(売り手の場合もあります)との賃貸契約から巻き直す必要があります。
2.事業承継は多くの再契約が必要になります。
次に(スモールM&Aの大半を占める)事業承継の場合には、企業買収と異なり、改めて雇用関係を含め、関係当事者の再契約・合意・同意・理解等そして当局の許認可等が必要です。
タイミングは難しいのですが、小売等不特定多数の顧客相手の商売は別として、どこかの段階で、大口の販売先(顧客)の理解を得ないことには、買収後の円滑な取引に支障が出かねません。(この点は、企業買収も基本は同じです)
仕入先や先に挙げた家主との関係も同様です。
今回のケースでは、α氏は両方で苦労しました。
α氏は実は既に副業を3年前からやっており、経営実績は事業承継関係補助金等申請に有利だと聴いていました。
ところが、良く調べると、個人は5年、法人で3年以上の経営実績(エビデンスとして各決算書が必要)が必要でした。(2024年4月現在。今後の公募の際に変更される可能性はあります。後記参照)
期待してしていた補助金での資金調達が出来なかったα氏ですが、その後各金融機関に打診し、辛うじて日本政策金融公庫から借り入れることが出来、ほっと一息つくことが出来ました。
しかし、α氏に次なる難問が降りかかってきました。
継承予定の花屋は、前記のとおり、数年前の大規模開発されたオフィスビルの中にありました。まさに一等地です。以前から、ビル敷地で商売していたD社長は優先的に入居が認められていたのです。大家は上場企業の大手デベロッパーの関係会社でした。
D社長とα氏が事業引継ぎの挨拶を兼ね、入居申込に行った際も大家企業の担当者は丁寧で親身になって手続きをしてくれました。ただ、提示された家賃額はD社長が払っている金額の数倍になっていました。
そして、数日後もたらされた入居審査結果は、「入居者としての基準を満たしていない」と謂う結論でした。
既存事業の実績規模や法人でないことも理由のようでしたが、詳細は開示されませんでした。
当該花屋の顧客の殆どは、このビルに入居している企業です。
慌てて、今や殆どビル街となってしまった、その街のビル群の中での入居可能場所を手当たり次第に当たりました。しかし、花屋の営業が出来そうな空きスペース、物件もなく、あっても更に高価な家賃~とても商売としてはペイ出来ない程度の金額提示を受けました。
ついに、ここに至って、α氏もM&Aを断念。D社長も結局廃業する他ありませんでした。
註:本件は私の周辺で実際に起こった事実に基づいて執筆しておりますが、守秘義務の観点から、基本的テーマに関係ない部分、一部の詳細・ディテールについては適宜修正を加えております。
もう少し掘り下げて学びたい方へ
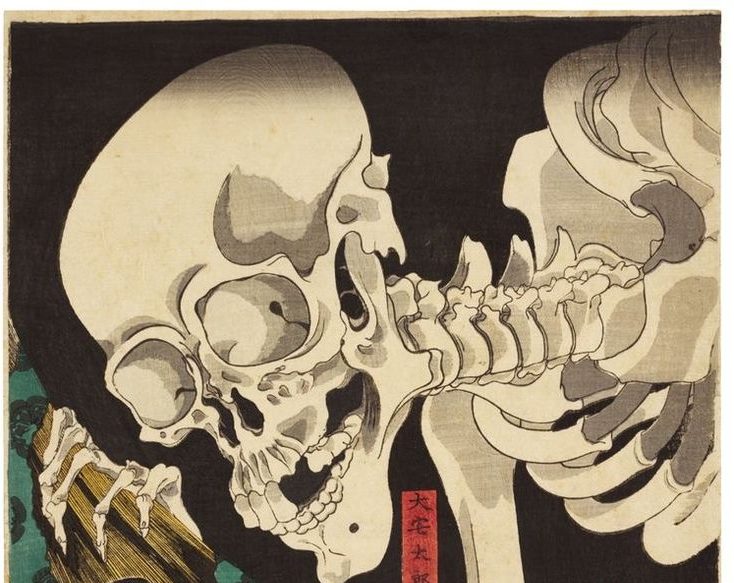
残念ながら、まだまだ個人はビジネスの世界では信用度が低いようです。
買い手を「法人」に限定して募集している「売案件」も現に存します。
M&A、特にスモールM&Aにおいては、買い手として個人が台頭しているのに、です。
個人の台頭に竿をさす気は毛頭ありませんが、このような状況では「法人成り」も検討課題の一つかも知れません。
税制の諸制度~法人税や所得税の絡みもありますので、安易な「法人設立・法人成り」は勧めませんが、
事業が常軌化し、年数百万円単位の売上が安定的に計上できる見通しが立った段階で、個人➠「法人成り」を検討しても良いと思われます。
是非、税理士さん他の専門家と相談されることをお勧めします。
先の事業承継関係補助金について触れておきますと、
平成6年度補正予算の承認を受けて、実施が予定されている経済産業省関連の補助金では、従来の「事業承継・引継ぎ補助金」が「事業承継M&A補助金」と改称されます。ただ名前を変えただけだろう…と謂う人もいます。
しかし、「名は体を表す」の言葉どおり、この名称に変えたことには経産省/中企庁も、今や事業承継の主流はM&Aだと認識が込められているのではないでしょうか。
その証拠に、例えば、PMI枠の新設、中堅企業を念頭に支援金額の一部アップ等の改正が予定されています。
まだ新しい公募要領は公表されていませんが、従来のルールでは、先に記したとおり、この補助金を利用出来る方は限定的でした。買収する側の要件として企業経営の事実を重視しているのは理解出来ますが、一般サラリーマンが、スモールM&Aで企業を買う時代に、果たして、それで良いのかと謂う疑問を持たざるを得ません。
参考までに、前回(第10次)の公募要領から「補助対象者」の定義を抜き書きします。
(今後の改正を強く期待しながら)
補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は受付印がないため、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
買い手を「法人」に限定して募集している「売案件」も現に存します。
M&A、特にスモールM&Aにおいては、買い手として個人が台頭しているのに、です。
個人の台頭に竿をさす気は毛頭ありませんが、このような状況では「法人成り」も検討課題の一つかも知れません。
税制の諸制度~法人税や所得税の絡みもありますので、安易な「法人設立・法人成り」は勧めませんが、
事業が常軌化し、年数百万円単位の売上が安定的に計上できる見通しが立った段階で、個人➠「法人成り」を検討しても良いと思われます。
是非、税理士さん他の専門家と相談されることをお勧めします。
先の事業承継関係補助金について触れておきますと、
平成6年度補正予算の承認を受けて、実施が予定されている経済産業省関連の補助金では、従来の「事業承継・引継ぎ補助金」が「事業承継M&A補助金」と改称されます。ただ名前を変えただけだろう…と謂う人もいます。
しかし、「名は体を表す」の言葉どおり、この名称に変えたことには経産省/中企庁も、今や事業承継の主流はM&Aだと認識が込められているのではないでしょうか。
その証拠に、例えば、PMI枠の新設、中堅企業を念頭に支援金額の一部アップ等の改正が予定されています。
まだ新しい公募要領は公表されていませんが、従来のルールでは、先に記したとおり、この補助金を利用出来る方は限定的でした。買収する側の要件として企業経営の事実を重視しているのは理解出来ますが、一般サラリーマンが、スモールM&Aで企業を買う時代に、果たして、それで良いのかと謂う疑問を持たざるを得ません。
参考までに、前回(第10次)の公募要領から「補助対象者」の定義を抜き書きします。
(今後の改正を強く期待しながら)
補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から 5 年が経過しており、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は受付印がないため、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。