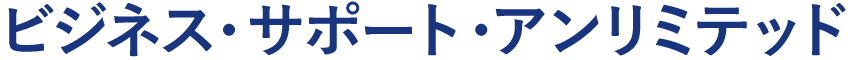「M&Aは怖い。リスクがある」と言う声はまだまだ聴かれます。
しかし、この世界では、M&Aに限らず、全てのビジネス/事業行為にリスクは存在します。
勿論、その性質、金額、規模、頻度、影響範囲等は様々ですが。
そもそも、リスクのないビジネスは存在しません。
例えば、ヒトを雇うこと自体もリスクです。不動産を購入するのもリスクが伴います。
新技術開発もリスクを伴います。新事業・新市場進出もリスク不可避です。事業撤退にもやはりリスクは存在します。
一方で、M&Aを上手く使えば、ヒトを手に入れることも、不動産を手に入れることも、新技術を手に入れることも、新事業・新市場を手に入れることも出来ます。勿論、事業撤退にもM&Aは使えます。
因みに、M&Aは資金調達方法としても使えます。
M&AにはM&A固有のリスクも当然あります。しかし、ここまでM&Aが普及し、今や経営の一手段となっている現況下、それらのリスクは各種事例の積み重ねを通じて、ほぼ解明・定型化され、対応策も用意されています。勿論、保険によるカバーも今日ではほぼ全領域可能となっています。費用対効果・誰が負担するか等の問題は残りますが。
例えば、M&Aのリスクと言えば、「買い」側のそればかりを喧伝する方もいますが、「売り」側にもリスクはあります。その最たる例が先のL社絡みの案件です。そして、当該記事でお示したとおり、これについても一定のリスク回避策はあるのです。
以下、著名なM&Aの失敗事例≒リスクと評されるものについてみていきましょう。
著名なM&Aの失敗事例研究~東芝と「ウエスチングハウス」の場合

2023年12月20日、超名門企業 東芝は74年の上場企業としての歴史に幕を引きました。
これまで、このブログでは私の周りで実際に起こったスモールM&Aに関する失敗事例をみてきました。
しかし、今回は有名企業による「失敗事例」を見てみましょう。
多くの方が、これらの事例を通して多くの人が「M&Aは怖い」「リスクが高い」と思い込んでいる節があります。
ここでは、M&Aで苦境に陥った企業の代表例として「東芝のM&A」について開示情報に則して見ていきましょう。
東芝はかつて日本を代表する総合電機メーカーであり、財界各団体のトップに何人もの人材を送り込んだ、所謂「名門企業」でした。また、例えば「ランプの世界6大発明」の2つを有する等「日本初」「世界初」を連発する高い技術力と歴史を誇っていました。
ノートPC「ダイナブック」はかつて世界トップシェアを誇りました。
その東芝が不正会計事件とそれを巡るゴタゴタで、すっかり世間の信用を失い、上場維持を巡り、様々な人物、機関が登場し、傍から見ていると、東芝はそれらに翻弄され続けたようです。
遂には最大の収益部門であった半導体部門までも売却する等迷走を続けた挙句、結局、上場廃止を選択せざるを得ない状況へと追い込まれていきました。その後の再建の道も厳しいとの声も聴かれます。
これらの経営不振及び東芝の信用失墜の総仕上げとなった不正会計(註1)発生の背景の一つとして、また連結業績悪化の要因として関係者の指摘が一致しているのが、
「2006年のウエスチングハウス(以下「WH」)の買収による躓き」でした。
もともと、日立、三菱等に比較し必ずしも盤石とは言い難い自身の財務体質に目を瞑り、東芝が約6210億円(東芝発表。54億米ドル、115円換算)もの巨額投資によって手に入れたWHは受託目標も果たせず、赤字受注を重ねて経営は悪化、更に当該M&A後に同社が買収した企業がトンデモナイ粉飾の塊だったことも判明し、二重三重に東芝を苦しめ続けます。
註1)一連の東芝の不正会計の萌芽=原型と言うべきものは、2004年当時赤字に転落していたPC部門立て直しの際に使われた「バイセル手法」でした。
ここで言う「バイセル」とは、具体的には、東芝が原材料を大量に安く仕入れて、それを下請けメーカーに売り(セル)、その後完成品を買い戻す(バイ)と言う一連の工程のことであり、それ自体は違法でもなんでもありません。が、この仕入量と(上乗せ)価格、買戻す量と金額を意図的にズラすことにより、一時的に表面上は期間利益を大きく嵩上げすることが出来る為、決算時の利益操作に悪用されていたことが判明しています。
こうした利益操作を通じて経営陣の粉飾に対する感覚がマヒしていったとみられています。
WHの不振については、その直後の福島原発事故による世界的脱原発の大きな流れの変化も確かに、その一因ではありましたが、そもそもチェルノブイリの事故以降、原子力ビジネスの成長力はあきらかに鈍化し、WHも大規模な原子力設備建設は当時は僅か数件しかなかったと言う事実が、既に買収時点ではありました。WHが受注した工事も、度重なる延期や最新の規制をクリヤーする為の追加コストが嵩み、経営は悪化します。
一部にM&A当時のDDが不十分だったと言う指摘があり、その点ではM&Aのリスクかとも思われますが、各種報道を具に読み解くと、本格的なDDそのものを実施しなかったのではないかと思われ、M&Aのリスクどころか、M&Aで当然踏むべき基本の手順を踏まなかったと言う、謂わば、M&A以前の問題であった可能性が高いと言わざるを得ません。
また、本件のように超巨大案件は様々な要素が複雑に絡み合って成功・失敗の要因を単純に決めつけたり、一刀両断するのは困難ですが、開示されている事実をフォローして積み上げていくと、以下の様な状況が浮かび上がってきます。
2000年頃の東芝は東南アジア勢の攻勢を受け、低成長・低収益に甘んじていたのは事実でした。しかし「B to C」の分野において広い裾野をもち、安定的な収益は上げていました。もっとも財務体質自体は必ずしも強固とまでは言えませんでした。
その結果、当時の経営陣は、まだまだ収益計上が可能な祖業の電機部門を含め、エンターティンメント部門なども「選択と集中」と称して次々に切り売りした挙句、一転して、必ずしも主流でなかった「B to B」分野への比重を拡大します。「今後大きな成長が期待される」と信じ込んだ原子力部門(と半導体部門)に資金や経営資源を注ぎ込みます。競合と比較し、明らかに脆弱な財務体質を直視することもなく。
一方で、当時の原油価格高騰、地球温暖化防止の観点から原子力発電に対する米国主体で起こった見直しの機運、所謂「原子力ルネサンス」なるものが多分に東芝の経営判断に影響を与えたことも想像に難くありません。勿論、その背景には当時の経済産業省/資源エネルギー庁の政策判断・意向がありました。
今、リンク欄にある当該M&A実行時の東芝のプレスリリース等を見れば、「これで東芝の未来は万全だ」的な楽観論が透けて見えます。こういうスタンスだったからこそ、当然気付くべき&押えるべき売り手(WH)の問題点や徹底したDDの指示の不在やその報告検証も先入観に左右された可能性があります。そして当初買収陣の一角だった丸紅が中途で離脱したのも、本件自体の有するリスクに敏感だったからかも知れません。
勿論、WHもそれなりの強みは有していました。同社が世界の主流であった加圧水型原子炉(PWR)のトップメーカーだったことは事実です。一方の東芝は世界的にはマイナーな存在だった沸騰水型原子炉(BWR)メーカーでした。
そのWHが売りに出た訳ですから当時、特に日本で注目を集めました。事実、WHと当時から近しい関係にあった同じく日本を代表する企業で、日本の原子力有力メーカーでもあった三菱重工業も入札に参加していました。当初、その落札価格は2000億円程度とみられていました。しかし、蓋を開けると、東芝は最有力とみられていた三菱重工業を蹴落とす為に、6000億円強の数字をを提示。この時点で投資機関や競合先を含む同業者からも「あまりに高すぎる買い物ではないか」との声が上がっていました。(註2)
この投資の結果、東芝は財務的にはWHの純資産額を上回る約3500億円を暖簾代として計上することとなります。そして、この償却負担が東芝を追い詰めていきます。(註3)
更に、WH関係の追加投資負担や各種損害賠償がその後も東芝に大きく伸し掛かってきます。
註2)価格交渉については、買い希望者間でも、売り手との間でも虚々実々の駆け引きが水面下で行われていたようで、それらに関する証言もいくつか公になっていますが、ここでは売主側が何度も入札をやり直しさせ、その度に値を釣りあげていった事実だけを指摘しておきます。
註3)日本と米国会計基準によるのれん代(営業権)の償却ルール
日本:無形固定資産として20年間(以内であれば、会社の判断でより短い期間で均等償却も可)毎年均等償却。
但し、税務上は、株式譲渡の場合、のれん代償却は認められておらず、企業の償却負担は小さくありません。
米国及びIFRS(国際会計報告基準):無償却。但し、毎年「減損テスト」(DCF法で評価替えし、当初金額と比較し差額分を減損処理)実施要。
なお、IFRSは従来は日本同様償却処理としていたが、2004年以降米国方式に転換。
現在、日本でもIFRS方式採用への転換が検討されています。
因みに、東芝はWHに関しては米国基準採用と称し「減損テストの結果、減損は不要」と主張続け、無償却のまま破綻を迎え、巨額の減損処理を迫られます。
振り返って、WHの来歴を見れば、もともとはGEと並ぶ米国の総合電機コングロマリットでした。
しかし、巨大化するにつれ経営は保守化し、業績は低迷、次々に主力事業を切り売りし、投資部門強化も裏目に出ます。この過程で原子力部門もBNLF(英政府保有の英核燃料会社)に売却されます。彼らは放送事業に活路を見出し、CBSを買収しますが、最終的にはバイアコムに買収されて消滅します。
結果的に、BNLFに買収された原子力部門がウエスチングハウスの名前を承継する形になったのです。
ところが、一時あれ程喧伝されていた「原子力ルネサンス」とやらも掛け声倒れに終わり、気が付けば雲散霧消していました。
一方、WHを買収したBNFL側も事情が変わってきます。もともと部分的民営化を見据えて米国のWHを買収したのですが、肝心の民営化が遅れている(最終的は同社は解体されます)状況下、WHが中国から受注し進めつつあった原発4基受託については「大変高いリスクがあり、納税者がそのようなリスクを負うべきでない」(アラン・ジョンソン貿易産業相)として売却することを決めたと表明します。
さて、M&AにおけるPMIの重要性は言わずもがなですが、この点でも東芝は終始買収された側=技術を保有しているWHに経営の主導権を握られ、ガバナンス不在のまま各種の事態発生に振り回され、追い込まれていきます。
2017年、遂に万策尽き、WHは米破産法第11章(日本の「民事再生法」に該当)の適用を申請します。
後発のハンディを乗り越え、世界的競争に打ち勝つ為には、トップメーカーを手に入れ、東芝全体のビジネス転換を図らねばならない、と言う気負い・先入観が、事態を冷徹に見通す眼を曇らせ、すべての判断を誤らせたのではないかと私は見ています。
つまり、本件はM&A固有のリスクと言うより、世界的なビジネスの潮流の変化を読み違え、机上の空論に近い「ビジネス転換」に固執し、強引に推し進めようとした「経営判断自体の誤り」の面が強い事例だったと考えています。
WHと東芝本業自身の業績不振で東芝は追い詰められていきます。既に粉飾は引き返せない規模にまで膨れ上がっていました。
WHの後日譚:
2018年、カナダの投資会社ブルックフィールドのグループ企業が46億米ドルで買収。
2023年、カナダのウラン生産大手のカメコとブルックフィールド・リニューアブルが、78億7500万米ドルで買収。(負債を除く株式価値は45億米ドル)
欧州のエネルギー危機、天然ガスの高騰により、世界的に、再び原子力への関心が高まってきた流れを受けたもののようです。
M&Aのリスク回避策 ~「NO!」と言えるFA

しかし、時に買収企業を経営危機に陥れることもあります。
先の東芝-ウエスチングハウスの事例の様に。
問題はM&Aが経営不振の真の要因だったのか否か、です。
東芝のケースは、複雑多岐に亘り、且つそれが相互に絡み合っており、規模も大きく、関係者も多く、様々な局面・要素があり、失敗の真の要因特定は限られた情報の中で明確に示すことは難しいですが、
通常、M&Aに求められる基本的ステップ、留意事項~特にDDとPMI(及びPMIを展望した合意契約書作成)が重要と考えます~を適格・確実に熟していけば、よりマシな結果になった可能性は高いと思われます。
そして、原子力発電及びWH社に対する過度の思い入れと言う経営判断上の要因が本失敗の看過出来ない要素だったと私なりに分析しています。
さて、このブログでは基本的にスモールM&Aに関するテーマを採り上げております。
スモールM&Aの場合は、相対的に関係する事象はシンプルで量的にも少ないケースが殆どですので、
買い手側は売り手企業のDDとPMI、売り手側は買い手側の信用調査、支払能力を主体に個別事情に向き合えば、多くのケースではM&Aに伴うリスクの大半は大幅に圧縮乃至解消されると思っています。
特に私どもは仲介でなく、FAに特化しておりますし、特にDDに注力しておりますので、安心してお任せください。
最近は業界でも報酬のダンピングが流行って(?)いるようで、私どもも例えば、ミニマムチャージ(M&A成功報酬のリーマン方式による算出法の例外)はスモール特割も用意しております。
しかし、ここでは、むしろ私どもは「着手金」(案件金額にもよりますが、案件単位で10~15万円)は、しっかりいただきます。
と言うことを、敢えて、ダンピング化の流れに抗して申し上げたいと思います。
一見、クライアントから手数料を毟り取る守銭奴に思えるかも知れませんが、私どもの報酬体系は実にシンプルで着手金と成功報酬のみです。(事前に合意いただいた必要経費除く)
その上で、以下に私どもが着手金を頂戴する理由・考え方を示します。
私どもは、今回のL社案件(2/19付ブログ参照)の潜在的要因として、一部の業界関係者になお存在している過度のインセンティブ給与体系に象徴される「多少の問題点があっても目をつぶり、なにがなんでもM&Aを成約を優先させる」と言う体質そのものも、その一つと考えています。
私どもはFAとして、あるべきスタンス(善良な管理者の注意義務)でDDを主体に精査した結果、具体的なリスクの所在、種類、金額、頻度、影響度等を調べ上げて提示いたします。
勿論、当該リスクの圧縮or解決可能な場合は、その対応策をお示しします。状況によっては、「問題あり、御社とのM&Aには適していない」と言う結論・レポートを提出することもあります。
(最終判断は無論、クライアント自身が決定)
つまり、目の前のM&Aについて、クライアント様に「NO! が言えるFA業者」でありたいと思っております。
自らの成功報酬より、クライアント様の利益・ベネフィットを優先させます。
そうなると、「百三つ」と言われている、この業界では、これだけ精力的に取組んでも、成功報酬と言う意味ではタダ働きになることも少なくありません。
そこで、せめて着手金をいただくことで、欲に足を取られることなく、クライアント様の為、公正・公平・適格なFAが出来るようにしています。
不適切な案件には、報酬に目が眩むことなく、自信をもって「NO! と言える」ことを心がけております。
ムダな経費は当然抑えるべきですが、必要な投資は行うべきですよね。
プロのFAと契約することをお考えになりませんか?
そして、どのようなFAを、どういう観点で選ぶか…が大事ではないでしょうか?
私どもは、受託したM&A案件につき、各種DD実施他を通じて当該M&Aが内包するリスクについて適切且つ正確に明示します。可能であれば圧縮策等、リスクの軽減が難しい、あるいは致命傷になりかね場合は謝絶案も含め、クライアントにお示しし、最終的なご判断をお願いしています。(検討の結果、謝絶するケースの方が多数です)
FAがいれば、100%リスクがなくなるとまでは言えませんが、
重要事項説明書やFA業務に対するスタンス等をヒアリング・確認する中で、
諸リスクに対する知見・ノウハウに詳しい or 強いFAを選ぶことは、リスク対応策としては極めて有効と思われます。
リスク回避策の一方策として、是非、ご検討ください。